 尺八追分 MUSE 272 尺八:庄司竹養
尺八追分 MUSE 272 尺八:庄司竹養[PR]この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
Last update: Jan. 2nd, 2014
民謡に関する知識は、全くと言って良いほどないし、また関心も無かった。それは現在でも殆ど変わりはない。但し、追分に関しては別格で、
「−江差追分と尺八に生きた−鴎嶋軒小路豊太郎と周辺の人々」 井上肇著、を読んで尚更興味が湧いた。小路(こうじ)豊太郎は江差に生れ、
かの神保政之助から「三谷」と「鈴慕」を習い、「江差追分」に尺八の手付けを行った先駆者であると知ったからだ。今日、民謡の伴奏に尺八は
付き物だが、この江差追分の手付けが、その嚆矢となった事は知らなかった。弟子の内に小林波鴎、高橋空山などがいる。小路豊太郎は晩年
に至って大正9年上洛し、勝浦正山の門を叩いて明暗真法流を習い、一方の小林波鴎は翌10年に同じく上洛し、こちらは小林紫山に師事した。
小路豊太郎は古典本曲に専念する為、小林波鴎は追分の独奏に磨きをかける為であった。残念ながら小林波鴎は帰郷して間もなく早世した。
追分のそもそもの発生の地は知らないが、北陸から陸伝いに北海道まで伝播したのかとも思う。虚無僧も良く吹いていたようで、外曲の部類に
属するとは思うが、虚無僧とて人の子、お布施の御礼に吹いたとしても、或いは追分を吹いて流して歓心を買ったのかも知れない。江差追分の
SP盤だけでも100種類以上出ていたようで、今となっては信じられないほど人口に膾炙したようだ。民謡尺八としての小路流は、2代樽田隆章、
3代松本晁章と継承されている。
追分 (Oiwake)
福田蘭童の「追分」は福田蘭童のページ(こちら)にアップしてあります。
上田芳憧、竹童の「追分」は上田流のページ(こちら)にアップしてあります。
浦本浙潮の「追分」は、明暗流のページからリンクしてある所(こちら)からお求め下さい。長管での演奏ですが、小林波鴎直伝+浙潮流です。
 尺八追分 MUSE 272 尺八:庄司竹養
尺八追分 MUSE 272 尺八:庄司竹養
このMUSE RECORD は所謂、複写盤(海賊盤)で、元はドイツからのライロフォン盤だと思います。
 追分忍路高島、雪に叩かれ NIPPONOPHONE 2396/2397 平野源三郎、三味線:駒助(尺八無し)
追分忍路高島、雪に叩かれ NIPPONOPHONE 2396/2397 平野源三郎、三味線:駒助(尺八無し)
 正調追分、三下り追分 NITTO 321
堀野鳳聲、尺八:塚谷旭堂(B面)
正調追分、三下り追分 NITTO 321
堀野鳳聲、尺八:塚谷旭堂(B面)
 追分(前唄、本唄) NITTO 2130
唄:中山豪一郎、尺八:小金井静童、三味線:小金井きよ
追分(前唄、本唄) NITTO 2130
唄:中山豪一郎、尺八:小金井静童、三味線:小金井きよ
 正調追分(前唄、本唄) ツル印 5384
尺八連管:加藤渓水・上杉渓童(連管とありますが独奏です)
正調追分(前唄、本唄) ツル印 5384
尺八連管:加藤渓水・上杉渓童(連管とありますが独奏です)
 追分 Asahi 1-B 尺八:加藤渓水
追分 Asahi 1-B 尺八:加藤渓水
 追分前唄、追分本唄・後唄 Teichiku C-3503
初代:松前ピリカ、三味線:原田栄次郎、尺八:木田林松栄
追分前唄、追分本唄・後唄 Teichiku C-3503
初代:松前ピリカ、三味線:原田栄次郎、尺八:木田林松栄
木田林松栄は津軽三味線の名手として知られているが、尺八を吹いているのは珍しい。残念ながら縁が欠けていて、本唄の出だしは
フェード・イン処理しました。
 尺八追分 NIPPONOPHONE 2406
尺八:西田彌五郎
尺八追分 NIPPONOPHONE 2406
尺八:西田彌五郎
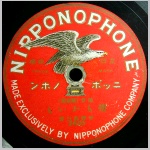 追分(新地節)櫓もかいも NIPPONOPHONE 2403 唄:平野源三郎、三絃:不明 (尺八は入っていません)
追分(新地節)櫓もかいも NIPPONOPHONE 2403 唄:平野源三郎、三絃:不明 (尺八は入っていません)
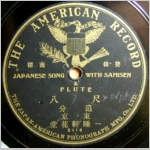 追分、(Oiwake) THE AMERICAN RECORD
2116 尺八:一睡軒花堂 (唄三絃:記載無し) 明治出張録音片面盤
追分、(Oiwake) THE AMERICAN RECORD
2116 尺八:一睡軒花堂 (唄三絃:記載無し) 明治出張録音片面盤
 追分、(Oiwake) MENOPHONE
939 尺八:小柳市太郎
追分、(Oiwake) MENOPHONE
939 尺八:小柳市太郎
 追分、(Oiwake) NITTO 1247
尺八:立花家扇遊
追分、(Oiwake) NITTO 1247
尺八:立花家扇遊
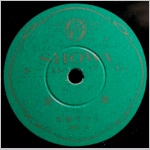 追分( 上・下 )(Oiwake) SHOWA 241
尺八:小金井静堂
追分( 上・下 )(Oiwake) SHOWA 241
尺八:小金井静堂
 正調追分(A・B) (Seichou-Oiwake)
NIPPONOPHONE 15353 尺八:本多翠竹、唄:本多千鳥
正調追分(A・B) (Seichou-Oiwake)
NIPPONOPHONE 15353 尺八:本多翠竹、唄:本多千鳥
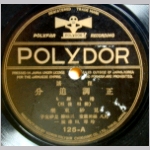 正調追分(前唄後唄・本唄 ) POLYDOR
125 唄:見砂東樂、尺八:福田蘭童、三味線:見砂定子、玲琴:田邊禎一
正調追分(前唄後唄・本唄 ) POLYDOR
125 唄:見砂東樂、尺八:福田蘭童、三味線:見砂定子、玲琴:田邊禎一
 正調追分(上・下 ) TEICHIKU
5349 尺八:酒井竹保
正調追分(上・下 ) TEICHIKU
5349 尺八:酒井竹保
 正調追分(上・下) Victor
53141 尺八:吉田晴風
正調追分(上・下) Victor
53141 尺八:吉田晴風
 正調追分(1・2) 教育レコード(Columbia) CK-16
尺八独奏:菊池淡水
正調追分(1・2) 教育レコード(Columbia) CK-16
尺八独奏:菊池淡水
追分(上・下) NIPPONOPHONE
2965/2966 唄:越中谷四三郎、尺八:後藤桃水
後藤桃水は「民謡の父」とも称されますが、そもそも民間伝承の「俚謡」を「民謡」と名付けたのは彼だと言われています。菊池淡水の師匠です。
我々、古典尺八を追及する者にとって重要なのは、長谷川東学師から「山谷」、小梨錦水師から「鈴慕、山谷、鶴巣籠」を伝承している点です。
録音は少ししか残されていないようですが、全部、民謡の伴奏みたいです。
松前追分、越後追分 Columbia 25455
吉木桃園、尺八:菊地淡水、後藤桃水
 正調江差追分(上・下)
スヒンクス 4527/4528 尺八連管:近藤雷童・徳田説三
正調江差追分(上・下)
スヒンクス 4527/4528 尺八連管:近藤雷童・徳田説三
井上肇氏に依れば近藤雷童は越後出身。明治23年に上京後「越後追分」を教授していたらしいが、翌24年に神保政之助宅に寄宿して追分尺八を習っている。このレコードの吹き込み年代は不明だが、神保政之助の影響が残っているのではなかろうか。
 正調江差追分(おしょろ高島・ろもかいも) (Esashi-Oiwake) NIPPONOPHONE
3438/9 尺八:梅田友治郎(B面三絃助奏あり)
正調江差追分(おしょろ高島・ろもかいも) (Esashi-Oiwake) NIPPONOPHONE
3438/9 尺八:梅田友治郎(B面三絃助奏あり)
 江差追分(前唄・本唄及び後唄) (Esashi-Oiwake) KING 41017 三浦為七郎、尺八:渡部嘉章、筝・三絃伴奏
江差追分(前唄・本唄及び後唄) (Esashi-Oiwake) KING 41017 三浦為七郎、尺八:渡部嘉章、筝・三絃伴奏
 江差追分、(Esashi-Oiwake) REGAL 65109 尺八:菊池淡水、榎本秀水
江差追分、(Esashi-Oiwake) REGAL 65109 尺八:菊池淡水、榎本秀水
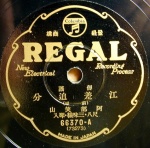 江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) REGAL 66370 阿部笑三、尺八・三味線・琴入り(名前記載なし)
江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) REGAL 66370 阿部笑三、尺八・三味線・琴入り(名前記載なし)
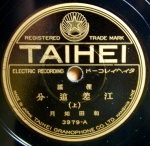 江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake)
Taihei 3979 和田如月、尺八:記載なし
江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake)
Taihei 3979 和田如月、尺八:記載なし
 江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) Columbia 26571
繁田雲濤、尺八:小金井静童、三味線・琴:記載無し
江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) Columbia 26571
繁田雲濤、尺八:小金井静童、三味線・琴:記載無し
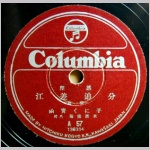 江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) Columbia
A-57 函青くに子、尺八:菊池淡水
江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) Columbia
A-57 函青くに子、尺八:菊池淡水
 江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) NITTO 3852 坂田光月、尺八:小金井正童、小金井静童
江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) NITTO 3852 坂田光月、尺八:小金井正童、小金井静童
![]()